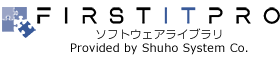2025年12月施行の所得税「基礎控除・給与所得控除」見直しの要点と実務対応のヒント
2025年12月から所得税の「基礎控除」と「給与所得控除」が大きく見直されます。この改正は、働き方や所得構造の多様化に合わせたもので、パート・アルバイト、フリーランス、高所得の給与所得者など、幅広い層に影響を及ぼします。
2025年12月1日より、所得税の基礎控除が最大95万円、給与所得控除が最低65万円に引き上げられます。これにより、給与収入が160万円以下の方は所得税が非課税となります。
ただし、住民税の基礎控除は変更されないため、住民税の課税対象となる可能性があります。また、社会保険の扶養認定基準(130万円の壁)も変更されないため、注意が必要です。
本日は、その改正内容をわかりやすく解説し、今後の年末調整や税務設計にどう活かすかを考えてみましょう。
1. なぜ改正されたのか?――背景と狙い
近年、日本の労働環境は「副業・兼業」「フリーランス」「テレワーク」といった多様な働き方が広がっています。一方で、税制では従来の控除額が据え置かれており、低所得層にとっては税負担が重く、高所得層にとっては恩恵が相対的に大きい構造が続いてきました。
そこで、令和7年度(2025年度)税制改正では、以下のような狙いで控除額の見直しが行われます。
- 低・中所得者の税負担軽減
基礎控除を一律48万円から最大95万円相当(特例期間中)まで引き上げ、給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円にアップ。これにより、特に年収が100万円~300万円程度の層の実質的な「手取り」が増加することが期待されています。 - 高所得者層への段階的縮小
一方で、合計所得金額が2,350万円を超えるあたりから基礎控除額を段階的に減少させ、2,500万円超では廃止。これにより、高所得層への控除メリットを抑制し、税収の確保を図ります。 - 扶養範囲・パート勤務の調整
いわゆる「103万円の壁」「130万円の壁」が、2025年以降はいったん約160万円まで緩和されるため、パート・アルバイト勤務者の勤労意欲を支援するとともに、扶養要件の見直しに柔軟に対応できるようになります(※ただし、特例措置は2025年・2026年限定で、2027年以降は再び下方修正されます)。
以上のように、今回の改正は「低中所得者の底上げ」と「高所得者の負担カバー」という相反する意図を同時に実現しようとするものです。特に、2025年12月以降に行う年末調整や確定申告では、これらのポイントをきちんと押さえておかないと、思わぬ所得計算ミスや税額差が生じかねません。
2. 基礎控除のポイント
2.1. 「一律48万円」から「所得に応じた段階制」へ
- 改正前(令和6年分まで):所得金額にかかわらず、一律48万円
- 改正後(令和7年分以後):合計所得金額に応じて最大58万円まで引き上げ、一部所得帯では段階的に減額
具体的には、合計所得金額(給与所得の場合は年収ベースのイメージ)の区分と控除額は以下の通りです。
| 合計所得金額 | 基礎控除(改正後) | 旧制度との比較ポイント |
| ~2,350万円以下 | 58万円 | 旧:48万円 → 新:58万円(+10万円) |
| 2,350万円超~2,400万円 | 48万円 | 旧と同じ |
| 2,400万円超~2,450万円 | 32万円 | 旧:48万円 → 新:32万円(▲16万円) |
| 2,450万円超~2,500万円 | 16万円 | 旧:48万円 → 新:16万円(▲32万円) |
| 2,500万円超 | 0円 | 旧:48万円 → 新:0円(▲48万円) |
- ポイント①:低中所得層のメリット
合計所得金額が2,350万円以下であれば、全員が58万円の基礎控除を受けられます。旧制度の48万円から10万円増えますので、年間の課税所得が10万円分減ることになります。 - ポイント②:高所得層の段階的縮小
合計所得が2,350万円を超えると、基礎控除が一律減少し、2,500万円を超えると控除ゼロ。所得が大きくなるほど控除上のメリットがなくなる仕組みです。
2.2. 「基礎控除の特例」――2025・2026年限定の上乗せ措置
令和7年分・令和8年分(2025年12月~2026年)限定で、さらに低中所得者に「特例上乗せ」が適用され、最大で「基礎控除95万円相当」にまで拡充される期間があります。対象と控除額は以下の4段階です。
| 合計所得金額 | 基礎控除(標準+特例) | 上乗せ額 |
| ~132万円以下 | 95万円(58+37) | +37万円 |
| 132万円超~336万円以下 | 88万円(58+30) | +30万円 |
| 336万円超~489万円以下 | 68万円(58+10) | +10万円 |
| 489万円超~655万円以下 | 63万円(58+5) | +5万円 |
| 655万円超 | 58万円 | なし |
- 対象イメージ:年収ベースで約850万円まで
たとえば、給与所得者の年収ベースで「850万円以下」の方(合計所得655万円以下に相当)は、この上乗せ措置を受けられます。 - メリットの実例
- アルバイトやパートで年収(給与収入)が103万円以下の方の場合、従来であれば「給与所得控除55万円+基礎控除48万円=合計103万円」が非課税ラインでしたが、2025年12月以降は「給与所得控除65万円+基礎控除95万円=合計160万円相当」まで非課税になります。
- つまり、所得計算上は「103万円の壁」は大幅に緩和され、勤労意欲の醸成が期待できます。
- 注意点:2027年以降は特例廃止
ただし、2027年(令和9年)以後はこの特例上乗せが廃止され、基礎控除は再び一律58万円に戻ります。したがって、所得設計や就業形態を決める際は「2025・2026年だけ大きな恩恵がある」ことを念頭に置きましょう。
3. 給与所得控除のポイント
給与所得控除とは、会社員・パート・アルバイトなど「給与所得者」の方が、給与収入を得るために使った必要経費相当を一律で差し引く制度です。2025年12月以降は以下のように変わります。
3.1. 最低保障額の引き上げ
- 改正前(令和6年分まで):給与所得控除の最低保障額(年収いくらでも)55万円
- 改正後(令和7年分以後):最低保障額を65万円に引き上げ
たとえば、年収100万円の給与所得者であれば、これまでは「100万円-55万円=所得45万円」に課税されていましたが、2025年12月以降は「100万円-65万円=所得35万円」になります。つまり、課税所得が20万円減ることになるので、その分所得税・住民税の負担も軽くなります。
3.2. 各年収帯における控除額のイメージ
詳細な「早見表」は国税庁が公表予定ですが、代表的な区分をざっくり整理すると以下のとおりです(年収は給与等の収入金額)。
| 年収(給与等収入) | 給与所得控除(改正後) | 旧・新の比較イメージ |
| ~190万円以下 | 一律65万円 | 旧:一律55万円 → 新:65万円(+10万円) |
| 190万円超~360万円 | 収入金額×30%+18万円 | 例:年収300万円なら「300万×0.30+18万=108万円」(旧:300万×0.30+18万-10万円)等、若干の微調整あり |
| 360万円超~660万円 | 収入金額×20%+54万円 | 同上 |
| 660万円超~850万円 | 収入金額×10%+120万円 | 同上 |
| 850万円超 | 一律220万円 | 旧:年収850万円超は一律195万円 → 新:220万円(+25万円) |
- 注1:厳密には、ものすごく細かい「端数処理」や「下限設定」がありますので、年末調整時には国税庁の公表する正式な「給与所得控除後の給与等の金額の早見表」を必ず参照してください。
- 注2:年収が高いほど、「一律220万円」という上限額まで到達しやすくなるため、給与所得控除の増減は「低~中所得層にメリットが大きい」と理解しておきましょう。
4. 実務対応のポイント
4.1. 年末調整・源泉徴収票の変更
- 適用タイミング
・年末調整:2025年12月1日以降に支払われる給与分から、改正後の「給与所得控除後の金額表」を使用
・源泉徴収票:2026年(令和8年)1月以降の支払分について、改正後の税額表を利用 - 扶養控除等申告書の様式改訂
2025年10月頃までに、新たな扶養控除等申告書が国税庁から公表されます。とくに「基礎控除申告書」「特定扶養控除申告書」の記載欄が追加・変更されるため、年末調整前に従業員(扶養親族のある方など)へ配布し、記入内容を正しく確認しましょう。
4.2. 社会保険・住民税への影響
- 住民税の基礎控除・給与所得控除にも波及
住民税についても、概ね同時期(2026年度分)から同様の控除額変更が行われます。したがって、「住民税の非課税ライン」も事実上引き上げられ、住民税の扶養範囲なども変動します。 - 社会保険料には影響なし
健保・厚生年金・雇用保険料などの社会保険料計算には、今回の所得控除改正は直接影響しません。ただし、手取りが増えることで、結果として家計設計や給与交渉の判断材料になることは覚えておきましょう。
5. 具体的に何が変わる?――労働者・会社ごとの事例
5.1. 例:年間給与150万円のパートAさん(扶養内で働く主婦)
- 旧制度
- 給与所得控除:150万円×30%+18万円=63万円
- 基礎控除:48万円
- 合計控除:63万円+48万円=111万円
- 課税対象所得:150万円-111万円=39万円
- 改正後(2025年12月以降)
- 給与所得控除:150万円×30%+18万円=63万円 → 最低65万円まで引き上げられるため、実際は65万円
- 基礎控除(特例措置適用):年収150万円は合計所得132万円超~336万円以下に該当するので、88万円(58万円+30万円)
- 合計控除:65万円+88万円=153万円
- 課税対象所得:150万円-153万円=0円(非課税)
→ これまでは39万円課税対象があったのが、改正後は0円になるため、所得税・住民税ともに完全に非課税となります。
5.2. 例:年収500万円の会社員Bさん
- 旧制度
- 給与所得控除:500万円×20%+54万円=154万円
- 基礎控除:48万円
- 合計控除:154万円+48万円=202万円
- 課税対象所得:500万円-202万円=298万円
- 改正後(2025年12月以降)
- 給与所得控除:500万円×20%+54万円=154万円 → 旧制度のまま、最低65万円を超えるので変更なし
- 基礎控除(特例措置適用):年収500万円は合計所得336万円超~489万円以下に該当するので、68万円(58万円+10万円)
- 合計控除:154万円+68万円=222万円
- 課税対象所得:500万円-222万円=278万円
→ 課税対象所得が20万円減るため、所得税であれば約4~5万円、住民税であれば約3万円程度の負担軽減になります。家族手当や住宅借入金等特別控除の影響は別途考慮が必要ですが、純粋に控除額の増加だけでも負担が緩和されることがわかります。
6. まとめと今後のポイント
- 改正時期を正確に把握する
- 2025年12月1日以降に支給される給与から「新しい控除額・早見表」が適用される。
- 年末調整・源泉徴収票の作成時期には、社内の経理・人事担当者が混乱しないよう、早めに改正内容を周知しましょう。
- 扶養範囲・パート就労設計の見直し
- 「103万円の壁」「130万円の壁」は一時的に解除され、160万円前後まで扶養内勤務が可能になる。しかし、2027年以降は再び下がるため、将来的な収入設計も視野に入れておくこと。
- 高所得者の控除狙いは縮小傾向
- 合計所得2,350万円超の給与所得者やフリーランスは、基礎控除額が段階的に減少するため、ふだんから経費計上やふるさと納税など、別の節税手段を検討する必要があります。
- シミュレーションを活用しよう
- 税理士ソフトや年末調整システムは、2025年10月頃から新制度に対応したバージョンがリリースされる見込みです。事前に試験版を使ってシミュレーションをしておくと、年末の混乱を避けられます。
- 一般向け・従業員向けの情報発信
- 自社のWebサイトや社内イントラでポイントをまとめたFAQを作成し、パート・アルバイトの方、扶養家族のいる方、高所得の方それぞれに合わせた解説コンテンツを発信しましょう。
――――――
以上が、2025年12月施行の所得税「基礎控除・給与所得控除」見直しの要点と実務対応のヒントです。今回の改正は、働く人の手取りや雇用機会に大きく影響します。企業側、個人側ともに正しい知識をもって、スムーズに対応していきましょう。